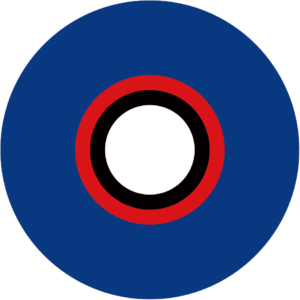見えないものを知覚する―生きる力を身につけるために/阿部雅世さん講演
PLAY DESIGN LAB
プレイデザインラボ 事務局
次世代の園を担う方々や、園経営に携わる方々が経営者としての真髄をつかみ、学びあう場として毎年開催されている「次世代園経営者セミナー」。2022年は8月23日~24日に実施された。今回は、ベルリン在住のデザイナー・教育者である阿部雅世さんの基調セミナーの内容をダイジェストでお届けする。
建築、デザイン、そして、教育
法政大学工学部建築学科卒業後、建築設計士としてキャリアをスタートした阿部さん。「見えるけど聞こえない」「聞こえないけど見える」といったような感覚体験を建築の機能的な要素として取り込み、誰も見たことがないものを可視化することに挑戦していた。
4年の実務経験を経て、1990年に渡伊。ドムスアカデミー工業デザイン科マスタークラスにて、まだ答えがない課題について、世界中の若者が集い答えを模索した。初めに取り組んだのは、普段は機能や価格でしか評価されない工業素材の美的・感覚的価値を見出し、その応用を提案すること。以降、デザインを、素材の感覚的な価値を発見するためのプロセスと捉え、工業製品や工芸品に落とし込み、目には見えない触覚や味覚、聴覚、嗅覚に訴えるデザインに取り組み続けている。例えば、音のデザイン。ある土地独自の環境音を新しい風鈴に変換し、観光客が音の思い出を自分の国に持ち帰ることができる製品を、土地に根差した陶芸、金物などの職人と共につくる。そのような感覚体験に焦点を当てた独特なデザインを数多く手がけ、感覚体験デザインの先駆者として、デザインの世界に独自のポジションを築いてきた。
阿部さんが教育に携わるようになったのは、2001年のこと。現実の仕事と大学教育のギャップを埋める試みとして、プロのデザイナーに自由な課題で指導してもらう特別授業が、ワークショップという形で行われるようになった時期、フランスの芸術学校から招聘され、3週間のワークショップに挑戦した。その際、教えるよりも育てる、教育の「育」に力を入れたいと考えたという。時代が変わる中で、教えられるものなどない。それよりも、自分で答えを探せる人材を育てることが大事だと考えたからだ。そこで、自らが一番面白いと思っているプロジェクトを持っていき、学生たちが、発見の連続である感覚体験デザインのプロセスを体験し、存分に味わうことができるプログラムを実施。そして、このワークショップの成果を展示したデザイン・ビエンナーレがきっかけで、その後、ローマ大学、フランスの陶芸美術館からもワークショップの依頼が入り、そのたびに、新しいプログラムを増やしていくようになった。
2004年、転機が訪れる。無印良品のデザイナー・原研哉さんが主宰する、HAPTICの展覧会のための作品制作依頼が来たのだ。HAPTICとは「触覚」の意味。当時できたばかりのUV印刷技術を使い、本のカバーの手触りをデザインすることにした。
「本のカバーは視覚的に内容を伝えるものだと思われがちですが、手のひらに直接ストーリーや感覚を訴えかけるデザインがあってもいいのでは、と考えました。点字用に開発された立体印刷、UV印刷技術が確立されたばかりのころであったこともあり、その技術をデザインに応用した、世界で最初の例として作りました。」(阿部さん)
感覚体験をベースにしたデザイン教育
2005年、ベルリン芸術大学の客員教授となり、本格的に教育の世界に足を踏み入れることとなった阿部さん。触り心地を表現する、言葉をデザインする、ハプティックディクショナリーを作る……これらのプロジェクトを通して、新しいデザイン教育を模索した。
日本語には触り心地-触った時に心に広がる感情-を表現するオノマトペがたくさんある。しかし、ヨーロッパの言語には、テクスチャーを説明する言葉はあっても、感情を表現する言葉は見当たらない。そのような気づきから「触り心地を表現するオノマトペ」は、デザインの技術用語として必要なのではないか、と考えていたという。その言葉は、果たしてデザインできるものなのだろうか。学内に実験的に設立したハプティック・インターフェース・インスティテュートに、9か国から集まった16名の学生たちと、まず「言葉」をデザインすることから始め、1週間で生まれた8つの言葉を、テクスチャーやオブジェ、プロダクトなどに落とし込むことに挑戦した。次の学期には、触り心地基本用語を網羅する、ハプティックディクショナリーの制作を進め、最終的に基本語となる40語を生み出し、「触り心地を表現する言葉」をデザインする楽しさ、それによって深められるデザインの質を、確信し、以降、このプログラムは、世界各地のワークショップで展開している。
ベルリン芸術大学で3年間の成果を上げたところで、今度は、エストニアの芸術大学から「感覚体験デザインと異業種の交流」を織り込んだ新しいカリキュラムを作ってほしいと依頼され、プロダクト学科の主任教授として2年務め、以降、様々な大学で教授職を歴任しながら、新しいプログラムを作ってきた。ベルリン芸術大学では触覚にフォーカスを当てたが、各感覚は切り離せるものではなく、デザインを総合的な感覚体験として捉える、感覚体験デザインにその視野を広げていった。現在は、日本の金沢美術工芸大学と、スロベニアのリュブリアナ大学の双方の客員教授として、二校協働のデザイン教育プログラムを実施している。
阿部さんが感覚を学ぶためのよりどころとしているという、アメリカの数学者、ロバート・フローマン著の『The Many Human Senses』には、人が何かを見る時、焦点を当てている対象から得る情報は脳に入る情報の1%ほどで、99%の情報は、ぼんやりと視界に入っている周辺視野から得ているという話が出てくる。後ろの気配やにおいなど、見えていないけれど感じている情報もあることから、「目以外の感覚を総動員して、五感で診たり、頭の中に思い描いて視たりしながら環境をとらえたとき、私たちは初めて「本当に見た」と言えるのではないか、と、思い当たったという。子どもは色々なことに興味を持っており、焦点を絶え間なく動かしながら、その周辺にあるすべてをとらえ、そして、目に見えていないものを「視る」ことを非常にうまくやっている。だからこそ、子どもの見る世界は豊かで広いのだ。いかにして大人を子どもの見える世界に戻すか、好奇心を取り戻して豊かな視点を養うか。教育者のためのデザイン教育の究極の目標は、そこにありそうだ。
「デザイン体操」と名づけたデザイン演習を始めたのは、2009年。それは大自然からは程遠い、都会の自然の中で数字やアルファベットに見えるものを探す、宝探しの演習だ。
小さな子どもは時間を忘れて熱中するが、多くの大人にとっては想像以上に難しいこの演習。しかし、毎日やっていると感覚が柔らかく広がっていき、必ず見つかるようになる。小さな環境の変化や周囲の見え方が変わるエクササイズなのだ。
子どもの感性を自分の中に持ち続けるということ
大学では、大人の固くなった頭を柔らかくするための試みは数々挑戦してきた阿部さんだったが、一度固くなったものをほぐすのは容易ではない。それよりも、柔らかい頭を持って生まれた子どもが、それを永遠に持ち続けることができれば、よいわけなのだから、と、生活環境を五感で知覚する様々な遊びを通して、子どもの感性や好奇心を活性化させる、子どものための感覚体験デザイン教育に取り組み始めて、すでに20年近くになる。
イタリアで行った「香りと色」のワークショップ。4、5歳の子どもたちに、様々な香りを嗅いでもらい、思い浮かぶ色を塗ってもらう。そして、それをみんなでカラーチャートにする。例えばラベンダーの香りの場合、多くの子どもたちが緑系の色を選んだ。大人の場合はラベンダーの花の色の紫を選びがち。情報が入ってしまい、純粋に香りの色を見ることができないのだ。無意識に頭の中のスイッチがそうしてしまうので、香りの色は子どもに聞く必要があるという。
ドイツのレッドドット・デザインミュージアムと共同で行ったEUのプロジェクトでは、子どもたちが日用品に使われている様々なマテリアルを体感で学ぶプログラムをつくって実践した。生活環境の質を体感で判断する力を身につけるための試みだ。同じ形で素材が違うものを触り、ミュージアムに展示されているプロダクトを触り、一台の自転車にどれだけ異なる素材が使われているかを触診し、と、ステップを踏みながら、体で学んでいく。すると、その先は、あらゆるマテリアルが気になるようになり、最後にミュージアム内をツアーさせると、まるでデザイナーのプロダクトチェックのように、プロフェッショナルな触り方をして、何も指示しなくても、展示されているプロダクトを確認していくようになる。たった3時間の演習でも、それを体験した後は、家に戻ってからも、身の回りのすべての素材が、気になるようになるだろう。気づくきっかけ、好奇心の入り口をつくることが、阿部さんのデザイン教育の基本だ。
2012年からは、シンガポールのデザインセンターの依頼で、子どもと教育者のためのデザイン教育のパイロットプロジェクトを、3年がかりで手がけた阿部さん。スピリットガーデンと名づけられた最初のプログラムは、シンガポールの生活のまわりにある、葉っぱや花や木の実を集め美しく並べたワンダープレートと大きな虫眼鏡、60色のオイルパステルを用意して始まる。子どもたちは、それぞれの葉っぱや花を、注意深く虫眼鏡で観察し、色を分析し、特徴を発見したら、それを、できるだけ本物のように絵に描く。60色のオイルパステルは、カラーチャートでもあり、色から入ることで、誰もが、すっと入り込むことができるプロジェクト。
どんな黄色なのか、どこに穴があり、どこで色が変わっているのかなど、特徴を捉える、科学的な観察を絵にしていく。そして、一人ひとりが描き上げた、本物のような葉っぱや花を切りぬき、ガラス窓の大きな面をつかって、色のついた影のインスタレーションに、全員で仕上げる。「自分の絵」から、それぞれの気づきを社会に発信する「私たちの作品」に昇華させることを体験することが、このプログラムの究極の学びでもある。このプロジェクトは、ちょうど、幼稚園と保育園の統合の動きがあり、先生たちの教育が求められていたタイミングで行われたので、各地から選抜されてきた先生たちを対象としたマスタークラスも実施した。その成果として、今では、パイロットプロジェクトの多くが、各地域の保育園や幼稚園の中で、実施されている。
子どもに質の高い体験をさせるためには、その目的を理解してサポートできる大人の存在が重要だ。子どもを育てることも大切だが、先生自身が自分を育てたり、自分の中の子どもを呼び戻したりすることも求められると阿部さんは語る。
「子どものために何かしようと思ったら、まずは大人を育てることが必要です。先生自身が元気で、子どもと同じ景色が見える状態になっていないといい教育は作れないのです。数の上で言えば、今の日本は、大人が圧倒的に多く、子どもは少ない時代なのです。だから、もっとたくさんの大人が子どもに関わってよいはずです。なぜそれができないのか。大人を育て直すことが、教育の質を上げることになるのではないかと思っています。」(阿部さん)
デザインや教育に長年携わってきたからこそ、大人のあり方やデザイン的発想の重要性を伝えてくれた阿部さん。五感をフルに使って頭を柔軟にし、子どものような新鮮な視点で世界を見渡し、子どもに関わっていくことの重要性を理解できた講演であった。