2025年で10年目を迎えるPLAY DESIGN LAB(PDL)は、あそびの研究所として様々な分野の専門家とともにあそびを深く研究し、新たなあそびを構想し、地域社会の課題の解決に貢献することを目指している。2025年6月27日、JAKUETS TOKYO MATSUBARAにて開催された「PLAY DESIGN LAB SESSION 2025」では、PDLの活動報告やトークセッションを実施した。この記事では、グッドデザイン大賞を受賞した「RESILIENCE PLAYGROUND PROJECT」のプレゼン、海外初出展となったミラノデザインウィークの報告、そして元陸上選手・為末大さんと医学博士・石川善樹さんのパネルトークの様子をダイジェストでお届けする。
 会場内の様子:当日は多くの来場者で賑わった
会場内の様子:当日は多くの来場者で賑わった
グッドデザイン大賞受賞プロジェクトを通じた気づきと未来

イベントは、2024年度グッドデザイン大賞を受賞した「RESILIENCE PLAYGROUND PROJECT」のプロジェクトメンバー、浅田駿太のプレゼンテーションから始まった。RESILIENCE PLAYGROUNDは医療的ケア児も遊べる遊具で、トランポリン型遊具のYURAGI、ブランコ型遊具のKOMORI、またがらなくても遊べるスプリング型遊具UKABIの3つが開発された。
医療的ケア児は日本に約2万人おり、医療の発達により救われる命が増えることで、今後さらに人口が増加することが予測されている。しかし、浅田たちの調査によると、医療的ケア児は「あそびたくても、あそべない」という課題を抱えていることが分かった。その課題解決を目指して、医師の紅谷浩之さんやオレンジケアラボのスタッフの方々など、地域に携わる様々なプレイヤーとともに協力してプロジェクトをスタートさせた。
「あそべない」を解決するために医療的ケア児と深く関わる中で見えてきたのは、実は誰もが自らの中に「あそび」を持っているということだった。あそび方を教えなくても、寝かせているだけでも医療的ケア児は自ら好きなあそびを楽しんでいる。浅田は「遊べないだろうという大人の先入観やあそび環境の作られ方が、本来持っているあそびを引き出す機会をなくしていたのではないか」と語った。
RESILIENCE PLAYGROUNDは開発から2年で130基以上納品されており、遊具を通して各地で今までにない風景が生まれてきている。医療的ケア児も健常児もごちゃまぜになって遊び、赤ちゃんやお年寄りといったあそびの風景から少し遠い存在も分断されず、自然と共存できるあり方に変化したのだ。
グッドデザイン大賞受賞後も、PDLは新たな遊具を世の中に届けている。大阪万博の「いのちの遊び場 クラゲ館」には、音の鳴るポールを納品。小さな揺れでも大きなフィードバックが得られるので、年齢や障がいの有無を問わず、誰もが楽しんでいる姿が見られている。福井市中央公園の「しろっぱ」には、RESILIENCE PLAYGROUNDなど様々な遊具を設置。重度障がい児をはじめとする子どもたちのあそびを、大人たちがさりげなく見守り、関われる空間となった。山口県の湯田温泉パークには、白狐伝説をコンセプトにした複合遊具を納品。市民とワークショップを行い、どのようなあそび場にすべきかを議論して形にしていった。
世の中の「しょうがない」、「仕方ない」といった当たり前は、ちょっとした工夫やデザインで変えることができる。誰もが好きなように遊び、幸せに生きられる次世代の優しい社会を作るきっかけとして、プロジェクトが役に立てると嬉しいと浅田は語った。
ミラノデザインウィークで実感した共遊空間の可能性

毎年4月に開催される世界規模のデザインの祭典・ミラノデザインウィークに2025年、初出展した。世界から838ブランドが参加し、1066件のイベントが公式に開催される中、ジャクエツは街の中心地にあるトリエンナーレ美術館前の広場にて「YUUGU」の展示を行った。今回、現地チームとしてミラノの出展に参加したPDL・チーフリサーチャーの加藤將則と赤石洋平、そしてPR担当のデイリープレス・川村美帆さんにより現地の様子が報告された。
ジャクエツの出展テーマは「Playful Sculptures」。プレイフルな彫刻、つまりアートのような遊具として、深澤直人さんデザインのYUUGU5点、そして椅子とテーブルを展示した。FRP遊具としては日本初となるヨーロッパの遊具の安全基準「EN規格」も取得し、イベントの3か月前から船便で輸送。海外向けにプレスリリースやリーフレットで発信し、改めてジャクエツのフィロソフィーを考え直してサイトに掲載した。
ミラノデザインウィークでは想像以上の反響があった。会場近隣の幼稚園児たちが毎朝遊具で遊びに来たり、親子連れやお年寄りが憩いに来たり、大学生がゼミの一環で集ったりと、ただ遊具を並べただけで公園の景色が大きく変化したのだ。また、遊具のあそび方を説明せずとも、子どもたちは自然に遊び始めていた。印象的だったのは、子どもたちが椅子を動かして遊具の中に置いたり、自由に並べて空間を作ったりする光景だった。自由な発想で自分らしいあそびを生み出すイタリアの子どもたちのパワーを感じた。
ジャクエツの出展内容は、デザイン雑誌『エル・デコ』、建築雑誌『ドムス』、大手経済新聞『IL SOLE 24 ORE』をはじめイタリアのメディアに多数掲載された。日本の『日経デザイン』でも紹介され、国内外に活動を広く紹介することができた。会場では子どもたちに向けたプロダクトとして様々なジャーナリストに興味を持ってもらい、活発に情報交換が行われた。
ミラノデザインウィークを通して、公園や広場といった空間にデザイン性のある遊具やファニチャーを置くことで、子どもだけでなく大人も一緒に集い、遊びながらリラクゼーションできる「共遊空間」が作れることを体感した。この経験を活かしながら、日本でも「共遊空間」を広めていきたいと3人は語った。
為末大さん×石川善樹さんのパネルトーク

最後は元陸上選手・為末大さんと医学博士・石川善樹によるパネルトークの様子をお届けする。以前よりオフィスを共有するなど交流のあったお二人は、あそびを核とした共創空間が地域課題にどう貢献するのか、そして地域住民一人ひとりのウェルビーイングを向上させる魅力的な場づくりについてトークを繰り広げた。
為末さんと石川さんは「ながく、あそぶ」とはどういうことなのか、調査したことがあるという。長く活躍する選手とそうでない選手の違いについて、アスリートの方々にインタビューして見えてきたのは、内的動機と外的動機、そして熟練度が絡み合うということだ。
アスリートは最初、あそびでスポーツを始める。純粋に楽しいという内的動機だ。次第に1秒でも速く、1mmでも遠くというように小さな改善を積み重ね、外的動機が原動力になっていく。ある時、夢や目標の限界に到達する。この時、熟練度はピークだ。年を重ねると限界を超えるのが難しくなり、他分野から学びを得ようとするアスリートが出現する。そして、最後は「この道を探求したい、追いかけたい」という、ある種悟りのようなあそび(内的動機)に戻ってくる。この考えは、為末さんの名著『熟達論』での「遊、型、観、心、空」の原型となった。
様々な人が集える地域の場を作るためには、あそびという内的動機から入り込める設計にすることが大事だと石川さんは語る。そして、その場に来ると小さな改善を目指したくなる刺激を受けたり、周囲には限界に挑戦して頑張っている人がいたり、多様な人々が集うことで他分野の学びが得られたりできると、「ながく、あそぶ」を実現できるのだろう。
為末さんとジャクエツのコラボレーション遊具「Kepler Tower」を開発した時、為末さんが意識したのは「気づかれないデザイン」だった。この遊具のテーマは体幹を鍛えることだったが、腹筋台を付けてもそれはあそびにはならない。腹筋を鍛えるトレーニングマシンがなくても、夢中であそんでいる内に腹筋を使い、体幹が鍛えられる仕掛けづくりを目指したという。
あそびの哲学者・ホイジンガは、それそのものが報酬であることをあそびの条件とした。体幹を鍛えることや学力を向上させることなど、大人の意図が伝わった途端に、あそびはあそびでなくなってしまう。また、ウェルビーイング向上につながるあそびとは、あそぶように不思議を探索できる空間だと二人は提案する。これも同じように、強制的に考えさせるのではなく、自ら疑問を持ち追いかけられる仕掛けが重要だと語った。
あそびの可能性を感じる場所として、石川さんは神社をあげた。塀で囲まれている寺に対し、塀がなくどこからでも入れるものの、鳥居という門がある。参拝の際はガラガラと大きな鈴を鳴らし、普段はあまり意識していない家族の健康や幸せを祈る。無意識の本音がふっと湧き出す不思議な空間だ。また、神社は断層の上にあるケースが多く、太古の人々が地場も含めて直感的に不思議を感じ取り、建設したのではないかということだった。
為末さんはこの話を受けて、あそびと神のつながりの例を出した。日本の蹴鞠は神や皇族と関連があるように、あそびは神や高貴なものと関連付けられることが多い。高貴な人が何かをすることを「〇〇あそばされる」と表現する。神社とあそびにつながりがあるのは、あながち外れていない気がすると為末さんは語った。
そして、石川さんはウェルビーイングのためには神聖な場所を作るという視点も重要だと提案した。縄文時代、集落が拡大するに従い人々は個々の家に住むようになり、次第に争いも増えていった。そして、コミュニティの結束を図るために集落の中心に墓を作るようになった。神様や先祖を祭り、自分たちがどこから来たのかを確認して団結するのだ。その意味で、日本の都市空間にとって祭りは重要な存在になると石川さんは語る。1970年の大阪万博から全国各地に広がった「お祭り広場」という存在は、使い方によっては住民の結束を図り、ウェルビーイング向上につながる可能性があるという。

多くの学びと気づきにあふれた「PLAY DESIGN LAB SESSION 2025」は、こうして幕を閉じた。多様なあそびを構想し、地域課題の解決につなげるヒントとなれば幸いだ。


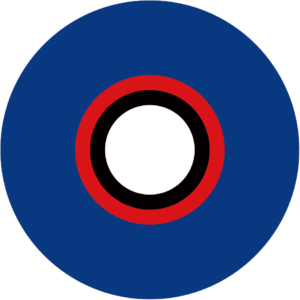
 会場内の様子:当日は多くの来場者で賑わった
会場内の様子:当日は多くの来場者で賑わった


