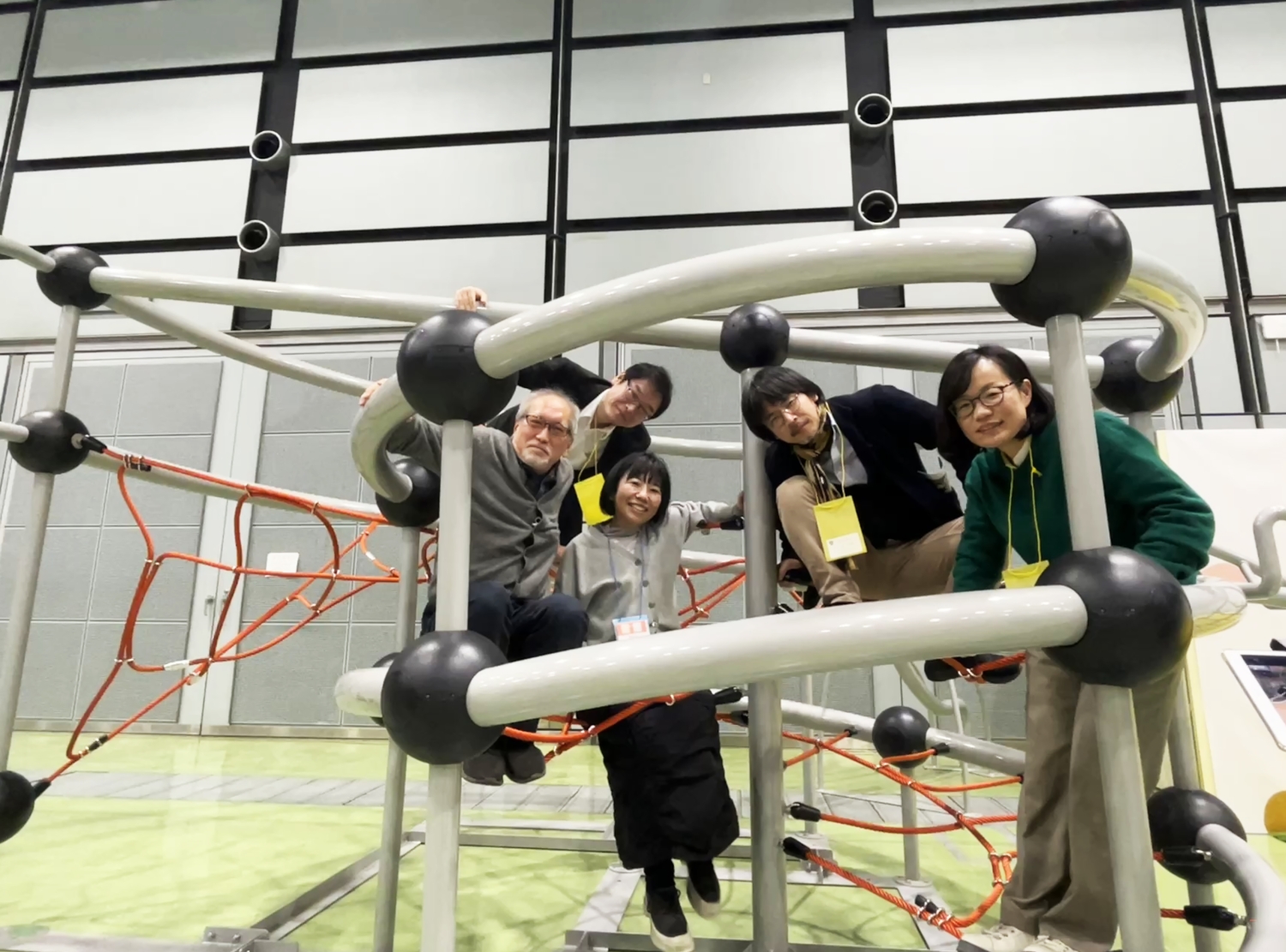アフォーダンスという語をつくったジェームズ・ギブソンは、環境にあるモノ(object)を2種類にわけました。
一つは地面(床)から離せるモノ、「遊離物detached object」です。遊離物は空気に完全に囲まれ、壊さずに動かせます。誰でもたくさんの遊離物に囲まれて暮らし、まわりの遊離物のレイアウトに注意して、小さな「模様替え」を繰り返します。動物も遊離物です。
もう一つは地面から離すことができないモノ、「付着物attached object」です。「地球の家具」と呼ばれる付着物は、その一部が地面と連続しているので、壊さなければ動かせません。
哲学はモノとは何かについての長い議論をしていますが、ギブソンのモノの説明はとても具体的です。自宅や職場にどんな遊離物あるか、すべてを記憶することは無理です。一方、街の付着物なら、どこに何があるかを指示できます。付着物は、場所と一体です。
からだのスケールに応じた付着物には、掴む、握る、足を置く、移動するなどのアフォーダンスを発見できます。付着物は手の操作から全身活動まで、たくさんの行為を与えています。
太古からヒトは森に暮らしました。この習慣は現代でも続き、どの街にも庭にも多くの樹木があります。樹木は進化をもたらしました。齧歯類やネコ科の動物などは、樹上へ生息域を広げ、母指対向性のある霊長類は、樹木生活で幹や枝を握りはじめ、そこから道具使用する人類が生まれました。
地中微粒子に根を張る付着物の樹木は、掘り起こせる遊離物です。21世紀にデザインされたSAPIENCEは、すでに樹木のように各地の園庭に「植えられて」います。
SAPIENCEは樹木ではありません。らせん構造、球状ジョイント、揺れる足場や踊り場などを持つSAPIENCEをここでは、「21世紀の樹木」と呼ぶことにします。どのような「樹木」なのか、アフォーダンス研究プロジェクトは、SAPIENCEとこどもたちの出会いと園庭を変える可能性について報告します。
大型付着物のSAPIENCEが、21世紀を生きるヒトに何をもたらすのか、いま新しい問いがはじまっています。(佐々木)


・踊り場のない遊具:支柱それ自体があそびになれるような遊具であれば、あそびの幅は大きく広がる
・らせん構造:上かららせんを見ると黄金比になっており、足場も不安定といったように、SAPIENCEはどこか自然らしさを感じられる形になっている。らせん部分の角度の調整にもこだわり。こどもが入れる角度か、つかまり立ちできるか、すべり台や手すりは脇に抱えられるサイズか。
・対象年齢:対象年齢を12歳までに引き上げた。従来の遊具よりも難易度は高い
・新しい踊り場:ある人にとっては動的に遊べる場所、ある人にとっては静的に座ってお話する場所といったように、遊具の持つ意味合いを変えたい。今後は公園などパブリックな空間への導入に力を入れていきたい。公園にSAPIENCEが入ることで、全体の空間が変わる可能性を秘めている。
(開発リーダー 藤井康介氏×デザイナー 本荘栄司氏インタビューより抜粋)
集まってくること、散らばること


SAPIENCE付近にこどもたちが近づいてきてから約3分。ネットの網目、ネットからポールへ、ポールからネットへの「次に一歩でいけるところ」を選択する。ポールのカーブに姿勢を沿わせながら、身体をスライドさせて移動する。好きなところからSAPIENCEに入ってきたこどもたちが、そのような動きをしていくと、SAPIENCEでは中心部に密に集まっていく時間帯が生じる。
一方、入口が限定されないということは、出口も限定されない。高いところからジャンプする、はしごを伝い降りる、滑り台のようにすべり降りるなど、こどもたちのSAPIENCEからの離れ方は様々であるが、離れる姿勢から、次の遊びへと続いていく。(山﨑)
いろんな向きと高さ


らせんの形状は移動の方向をある程度制約するともに、外に向かう遠心的ベクトルと内に向かう求心的ベクトルをともに含んでいる。一方、ネットの部分は明確な方向性をもたない。こどもは移動していくことで自ずとその先のこどもを意識する。内にいるこどもは外を見渡し、外にいるこどもは内が気になってしまう。


SAPIENCEはゆるやかな傾斜のらせんが地面から伸びている。そこにネット状のロープが掛けられ、様々な高さがシームレスにつながる形状になっている。こどもは遊びながら上下に視線を移動させ、その向こうにいる友達を見つけ、そちらに向かい、また多様な体の動きやルートを探っていた。(山本)
経路を共にする、交差する


踊り場のないSAPIENCEでの滞在の基本は移動となる。特徴的ならせん構造とジョイントがもたらす移動ルートの膨大なバリエーションによって、こどもたちは常に新たな移動ルートの発見に開かれる。「Yちゃん、見ててー!」の声に「やってみたろか!」とYが応える。見つけたルートを友だちに伝えること、それに挑戦し、共有することがコミュニケーションであることに、SAPIENCEは気づかせる。


支柱をつなぐジョイントは、移動ルートを結びつける場所でもある。ジョイントで一休みしていると、少し離れたところから友だちが近づいてきて、いつの間にかそこに踊り場ができる。違うルートから来た友だちとしばし話をして離れることもあれば、しばらく移動を共にすることもある。支柱やジョイントのバリエーションは、出会い方のバリエーションでもある。(青山)
常に揺れながら共振する


SAPIENCEの特徴の一つは揺れるネットでお互いの動きを感じることだ。ネットを登ってきたこどもの周りに数人が寄り集まる。登って来たこどもがネットを軽く揺らして、カエルの歌を歌い始めると、周囲も一緒に歌い出して合唱になった。二人のこどもがゲロゲロゲロゲロと歌いながらネットを揺らすと動きが伝わる。他のこどもも一緒に揺れる。ネット部分では必然的に揺れが伝わり、互いの行動が影響して共振が起こる。

SAPIENCEの上ではネットだけでなくポール上、ジョイントの上でもみんなモゾモゾと動き続けて、ちょうどいい姿勢を探る。それが不思議な姿勢でのコミュニケーションにもつながる。ポールにしがみついたり、もたれかかったり、常に動きながら自由な姿勢で遊びの相談が進む。そこに「マジで寒い」と言いながらこどもが築山から話しかけてきて、SAPIENCE 上のこどもたちがそちらを向いた。ここでは色々な姿勢で同じ出来事を共有する。(西尾)
<研究チーム>
佐々木正人(プレイデザインラボ フェロー・東京大学名誉教授)
青山慶(岩手大学准教授)
西尾千尋(甲南大学講師)
山本尚樹(弘前学院大学准教授)
山﨑寛恵(東京学芸大学特任准教授)
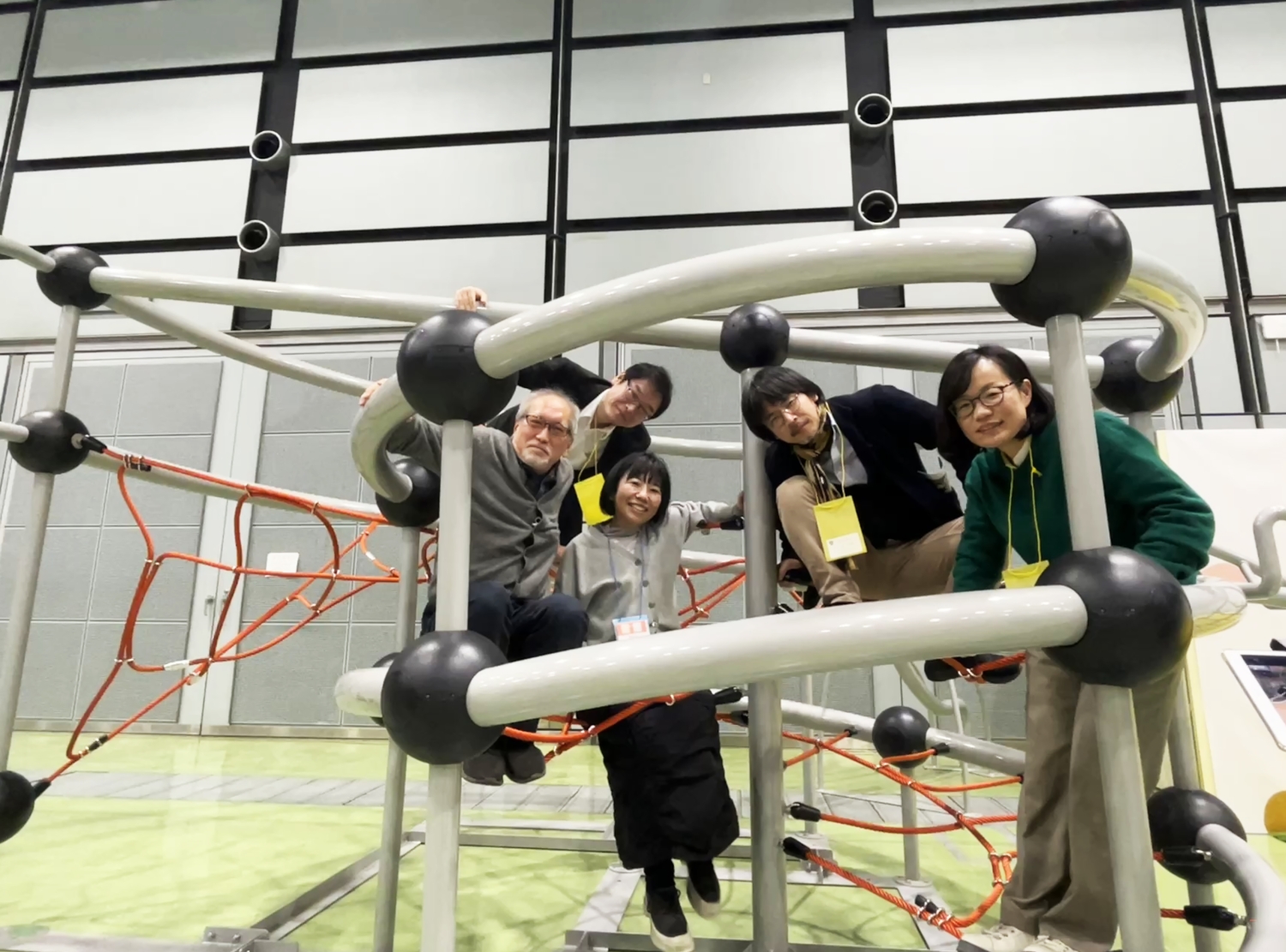
左から 佐々木名誉教授・青山先生・西尾先生・山本先生・山﨑先生
SAPIENCE のアフォーダンス(動画)