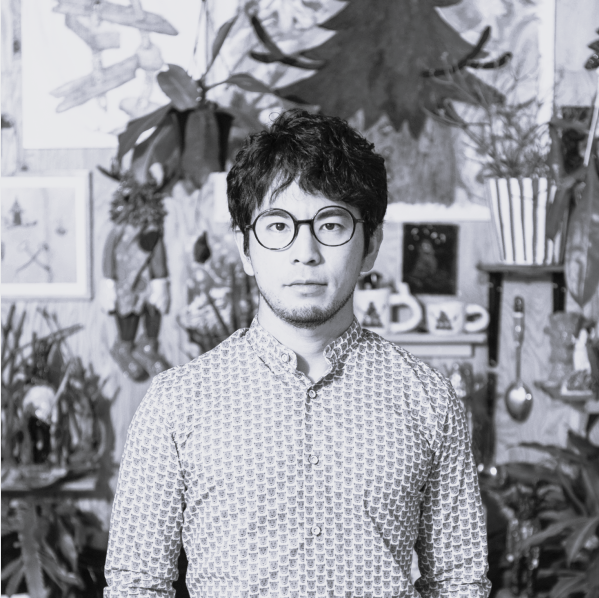人間と自然の関係性の中で浮上する曖昧さや疑問をテーマに絵画や彫刻、インタレーションなどの作品を国内外で精力的に発表し続けている平子雄一さん。平子さんにとって自然は、そしてアートはどのようなものか。また、今回ジャクエツとともに開発したハウス遊具への思いをお聞きしました。
堤防につくったひとりだけの秘密基地
—平子さんは自然と人間の関係性をテーマに作品をつくっていらっしゃいますが、平子さんにとっての自然のイメージはどのようなものですか。
平子:僕にとっての「自然」の原風景は生まれ育った岡山にあります。僕が育ったのは岡山市南部の干拓地で、山があって、海があって、田んぼがあって。まさに日本の田舎の景色と言えるところでした。
—自然が豊かな土地だったんですね。そこで、どのような子ども時代を過ごしたのですか。
平子:わりと活発な子どもでしたけど、みんなで仲良く遊ぶのはどこか苦手だったので、ひとりで林や藪に入って昆虫をとったり、釣りをしたりしていました。
干拓地には堤防がいくつかあったんですが、堤防沿いは河川敷みたいになっていて、そこにこっそり秘密基地をつくって遊んでいました。ジャングルジムも好きでしたね。だれかがまわりで遊んでいても、ジャングルジムの中心だけは自分の空間だという感じがしたんです。
秘密基地でもジャングルジムでも、周囲とはちょっと切り離された、閉鎖的な空間を独り占めできるのが、嬉しかったのかもしれません。
時代や社会によって揺れ動く自然と人間の関係性
—高校3年生でイギリスに留学したそうですね。留学を決めた理由を教えてもらえますか。
平子:僕は小学生の頃から絵を描くのが好きで、画家に憧れていました。現代美術の作品を見たことがなかったんですが、高校3年のときイギリスのYBA(Young British Artists)と呼ばれる人たちの作品集に出会って、すごく刺激を受けたんです。皆さん、素材も表現方法も、ほんとうに自由にやっていて。自分もこの方向で行きたいと思いました。それが留学を決めるきっかけになりました。
—イギリスでの留学生活はどうでしたか。
平子:ロンドンの美術大学に入学したのですが、そこでの教育は日本とはまったく違ったので、初めは戸惑いました。作品を作るプロセスを教えるのではなく、コンセプトを考え抜く力をつけさせる教育方法だったんです。
僕が絵を描くと、『どういうコンセプトで描いたの? そのコンセプトは何で成り立ったの?』って質問されて、それを元にもう一回描いてみると、『なんでこういう風に描いたの? なんでこういう配置にしたの? なんでこの色を使ったの?』と、さらに深掘りされるんです。分析して、それをコンセプトに当てはめて整合性がとれているかを検証する、それをずっと繰り返すので、作品を完成させるところまでは、なかなか行きつきませんでした。
大変でしたが、そのお陰で、物事に感覚的に向き合うのではなく、疑問を持って、丹念にリサーチして理解しようとするようになりました。
—平子さんが自然と人間の関係性への関心をもつようになったのは留学時代だそうですね。どのようなことがあったのですか。
平子:あるときロンドンの公園に行ったんですが、一緒にいた友人が『自然っていいよね』と言ったんです。そのなにげない一言に、僕は違和感をもちました。公園の植物は人間の手でよく管理されていて、僕が岡山で見てきた自然とはかけ離れていたからです。でも、自然は厳密に定義されているわけではないので、捉え方がそれぞれ違うのは当然だって気づいたんですよね。
それから、自然が歴史的にどのように位置づけられてきたか、産業との関係、宗教との関係などをどんどん調べていきました。その結果わかったことは、自然の捉え方は時代やその地域の人々の暮らしによって常に揺れ動いているということです。
たとえば、現代の日本に住む僕たちは森林を守らなければいけないと思っているけど、地域によっては木を切ることが生きるために不可欠だと考えている人々もいます。さらに言えば、森林を守るというのも人間中心の考え方で、森林の木々がほんとうに守られたいと思っているかはどうかはわかりません。
—自然と人間の関係は絶えず揺らいでいて、確定していないということですね。
平子:そうです。当時は僕自身も、自分がこの先どの方向に進もうか悩んでいた時期でした。だから、自然と人間の関係がとても不確定なものだと気づいたとき、バチッとハマったというか。僕はこの不確定性に向き合って、追い求めていこうと決めたんです。
地域や年代によって違う作品の受け止め方
—大学卒業後は、デンマーク、フィリピン、シンガポール、台湾、アメリカ、オランダ、香港、イギリスなど、各地で精力的に作品を発表してきたそうですね。
平子:はい。地域によって作品の鑑賞の仕方が違っていて、興味深かったです。
たとえばアジア圏の人々は、作品の表面に何が描かれているかに注目し、そこから何かを読み取ろうとする傾向があるように思います。
それに対して欧米の人々は、どうしてその作品を描いたのかを考えます。僕が大学でさんざん鍛えられた『コンセプト』ですね。これは大きな違いだと思います。
—アジア圏と欧米の国々ではそのような違いがあるのですね。作品の受け止め方などで、ほかにも気づかれたことはありますか。
平子:僕の作品には、頭部が木で、胴体が人間のモチーフがたびたび登場します。このモチーフの受け止め方も、年代や文化的背景によって様々なようです。
まず、人が植物を被っていると認識する人と、植物が人のような体をもっていると認識する人に分かれますね。
あと、すごく小さい子は拒絶して泣くこともあります。高齢の方にも怖いとおっしゃる方がいました。
僕なりに分析してみたんですが、自然や植物は美しく、大切にすべきものだという教育を受けた人たちには、植物と人間のハイブリッドであるモチーフが良いものっていう風に見えるみたいです。一方で、そういう教育を受けていない人たちには怖いものだと感じられるんじゃないでしょうか。
自然は、時として非常に恐ろしいものですよね。山も海も迂闊に奥深く入っていくと帰ってこられないかもしれない危険な場所です。そういう恐れや畏怖の念が心の奥底に残っているのかもしれません。
アートの原点は、自分は何が好きか、なぜ好きなのかを意識すること

平子雄一氏の絵画作品の一部
—現代アートの世界で活躍してきた平子さんが、遊具の世界に足を踏み入れました。そのときの気持ちを教えていただけますか。
平子:アートを発表する場やアートが波及する範囲は限られているので、違うエリアで自分が納得する形で発表したい気持ちはずっとありました。
僕の作品が遊具にフィットするのかどうか不安でしたが、やってみないことには何が起こるかわからないですよね。アートの世界は居心地がいいけれど、ここで固まってしまったらいけないという危機感もあり、思い切ってやってみることにしたんです。
もうひとつの理由は、子どもたちにもっとアートに触れてほしいと思ったことです。
僕は学校の図画工作の授業でも、もっとたくさん作品を鑑賞したほうがいいと考えているんです。色々な作品に触れて、自分はどの作品が好きなのか、どうして好きなのか、その作品から何を感じたかを考えることは、とても大事です。それは自分と向き合うことでもありますし、アートの原点とも言えます。
だから、僕の作品が遊具になって、小さな子どもたちに楽しんでもらえるなら、とても嬉しいことだと思ったんです。

—遊具「THE HOUSE」の構想から完成までには3年余りがかかったそうですね。
平子:遊具を作ってみようと決めたものの、いざ取り組んでみると、どうすればよいかまったくわかりませんでした。遊具は、子どもたちが遊びながら体のバランスの保ち方や人とのコミュニケーションの仕方を身につけられる、とても優れた道具だと思うんです。でも、僕にそれが作れるだろうかと考えると、できる気がしなくて。悩みに悩んだ末にようやく思いついたのが家、『THE HOUSE』だったんです。自分と向き合うこともできる、閉鎖的空間というのかな。
もちろん、たくさんの子どもたちに入って遊んでもらいたいですけど、入らない子がいても、それはそれでいいかなと思っています。
一般的にアートは見るもので、作品と鑑賞者との間に距離がありますよね。でも、この遊具は子どもたちが中に入り込んで遊ぶことができます。それは今までの僕の作品ではなかったことなので、僕なりの新しいチャンネル、伝える方法を見出した気がするんです。
—「THE HOUSE」の中には、頭が木で体が人間のモチーフも静かにたたずんでいますね。
平子:家の中に見慣れない不思議なキャラクターがいたら、子どもたちはきっと『あれ、なんだろう?』と疑問に思いますよね。そこから会話が生まれたり、想像をふくらませたりしてくれるかもしれない。
僕は子どもたちに、いつもたくさん疑問に持つようになってほしいんです。長く続く人生で、最初からこんなもんだと決めつけて生きていくよりも、これなんだろう?って疑問をもって生きたほうが楽しいんじゃないかな。僕の作品がその疑問のトリガーになったらいいなって思っています。